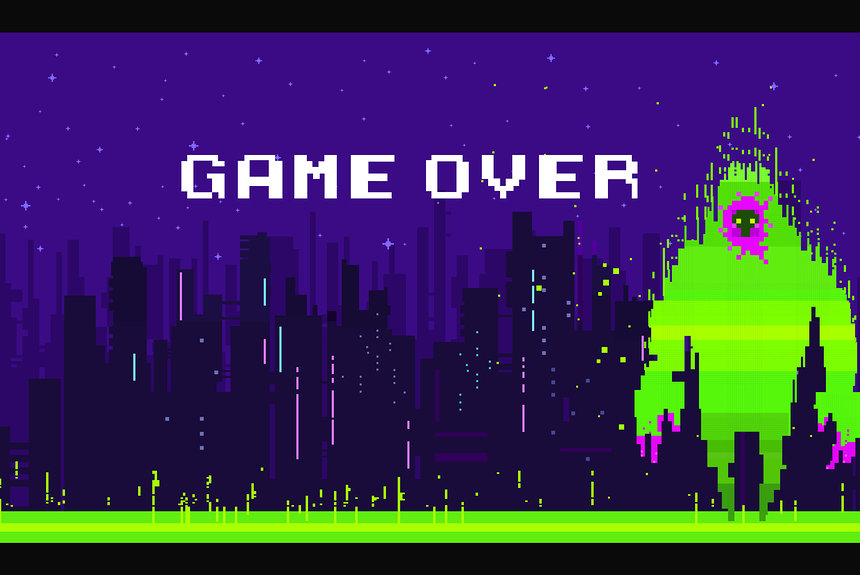個人・少人数で作られたゲーム=インディゲーム
ここ数年、年を追うごとにインディゲームの盛り上がりが加熱している。リリースされるインディゲームの本数が増加するというだけに留まらず、インディゲームイベントの規模も大きくなってきた。たとえば、毎年京都で行われる国内最大のインディゲームイベント『ビットサミット』は、2013年時点では来場者200人という小規模なイベントだったが、2018年時点では来場者数1万人をこえる規模に成長。また、東京で行なわれるインディゲーム即売会イベント『デジゲー博』も、2013年時点の来場者600人から、2019年時点で2000人まで規模を拡大している。
インディゲームとは、「個人」を意味する「インディビジュアル」と「ゲーム」を組み合わせた造語で、個人あるいは数名程度の少人数で開発するゲームのことを意味する。プロが開発した作品でも少人数で開発したものであればインディゲームと呼ばれるため、音楽のインディレーベルに近いと言えるだろう。
何が違う? インディゲームとビジネスゲーム
個人あるいは数名程度と書いたが、では、一般的なゲームメーカーが作るタイトルはどのくらいの人数で作られているのだろうか。もちろん、タイトルによっても異なるが、大抵は100名~1000名といった規模で作られている。正確な人数は知らずとも、ゲームをクリアした際に流れるスタッフロールを見たことがあれば、相当な大所帯で作っていることが分かってもらえるだろう。
では、スタッフの数の違いが、ゲームの内容にどんな違いをもたらすのだろうか? 100名~1000名といった規模で開発するビジネスゲームは、最先端の美麗なCG、豪華な声優陣など、ゴージャスな内容を盛り込むことができる。というか、ゴージャスな内容にせざるを得ない。なぜなら、ゲームマシンはよりゴージャスな内容が作り出せるように進化を続けてきたからだ。当然、ゲームファンはマシンの性能に見合ったクオリティをゲームに求める。そして、ビジネスである以上、100名~1000名といったスタッフ分のコストを回収しなければならない。
このためビジネスゲームは、大きなコストを確実に回収できるよう企画する。たとえば、対戦や協力といったマルチプレイを前提とし、繰り返し遊び続けられるようにしたり、新キャラクターや新装備を追加できるようにしてガチャやダウンロード販売といった形で売り上げを上げられるように企画されている。また、一般的なユーザーが慣れているゲームシステムをベースとし、斬新な要素は最低限に抑えるといったことも行なわれることがある。
こういった傾向から、コンシューマゲーム機であれば『Call of Duty』シリーズのようなオンライン対戦要素を持ったゲームがリリースされやすく、スマートフォン向けのゲームであれば、『Fate/Grand Order』をはじめとするような、キャラクター収集型のRPGがリリースされやすい。
『Fate/Grand Order』配信4周年記念映像
一方、少人数で作るインディゲームは、ビジネスゲームほどのボリュームを実現できない反面、コスト回収のハードルが低い。売れることにこだわらず、開発者が実現したいものを作ることも夢じゃない。このため、極めて作家性の強いゲームが登場する。たとえば大ヒットインディゲーム『UNDERTALE』のように、モンスターを倒す必要がないRPG。
誰も死ななくていいやさしいRPG『UNDERTALE』
あるいは、『VA-11 Hall-A』のように、サイバーパンクの世界観でバーを舞台にした人間模様を描く意欲作。
『VA-11 Hall-A』(Nintendo公式チャンネルより)
また、『198X』のように、1980年代に流行ったアーケードゲーム数作をオマージュとして取り入れたアドベンチャーゲームもある。
『198X』(Nintendo公式チャンネルより)
いずれも、「売れるゲームを考えよう」「採算を考えて企画しよう」という方向性からは生まれてこない作品だ。
作品情報
- 『UNDERTALE』
- 『VA-11 Hall-A』
- 『198X』